医 療 で
支 え る 仕 事 。
 Sponsored by
Sponsored byこのメディアはFMF胎児クリニック東京ベイ幕張を
スポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
日本ではまだ、生まれる前の赤ちゃん「胎児」を専門とする医療従事者が、圧倒的に足りていません。
当メディアでは、-1才(胎児)からの医療に関わる仕事「胎児医療」を
紹介しています。
1人でも多くの医療従事者に興味を持っていただき、
日本の「胎児医療」現場を変えるきっかけとなることを願います。

FMF胎児クリニック東京ベイ幕張は、-1才からの医療「胎児医療」の普及と人材育成を目指すクリニックとして、高度な超音波検査や遺伝カウンセリングに力を注いでいます。英語でのカンファレンスや研修制度などを通して、医療従事者個人のスキルアップを促し、専門性の高いチーム医療として、生まれる前からの命にできる健康診断「胎児ドック」に取り組んでいます。
胎児医療は、日本ではまだ馴染みのない分野ですが、海外では医療機関に「胎児科」があることが一般的です。海外の胎児科では、お腹の中の赤ちゃん(胎児)も1人の患者として扱われますが、日本の民法上ではまだ胎児を1人の患者とするかどうかの倫理的な議論が検討されている段階です。
日本でも、胎児医療を必要としている妊婦さんやご家族は多くいます。「胎児医療は身近なもの」という社会を実現するには、医療保険制度の課題解決だけでなく、各専門の職種を担う医療従事者が増えることが必要とされています。

妊婦健診の胎児版「胎児健診」として行われるのが「胎児ドック」であり、赤ちゃんの全身の健康状態のチェックを行います。超音波検査や遺伝カウンセリングなどを通して、赤ちゃんが先天的な病気や異常を抱えていないか、もし見つかった場合はどのような治療やサポートが必要なのかなどを検討します。

日本ではまだ「胎児医療」を専門とする医療従事者が少ないからこそ、これから新しい専門性やスキルを身につけてキャリアを切り開いていきたい方にとっては、この分野への挑戦が、今のキャリアに変化をもたらす大きなきっかけになります。

生まれる前の赤ちゃんを診る「胎児医療」は、日本ではまだ専門家が少ない分野です。しかし、海外では一般的であり、超音波検査や遺伝カウンセリングを通じて胎児の健康を支えています。
この仕事に就く「これまで胎児医療を知らなかった医療従事者」たちは、学び続けられる環境や専門性を深められる経験、そして何よりチームで命を支えるやりがいに魅力を感じ、成長していきます。医療従事者としてのあなたの情熱を「-1才からの医療」に向けてみませんか。

必ず指導者と
一緒に診察に入る
「マンツーマン
OJT」
シミュレーターを使った
トレーニングで
スキルを向上
座学を設けた勉強&レクチャー会で
専門知識を高める
学会や研修
セミナー参加の
費用サポート
FMF胎児クリニックでは、「胎児医療」未経験の若手の方でも成長できる教育体制を整えています。入職後はマンツーマンOJTやシミュレーターを活用した技術研修を通じて、着実にスキルを磨けます。さらに、学会参加や海外研究の機会もあり、より広い視野で専門性を高められます。

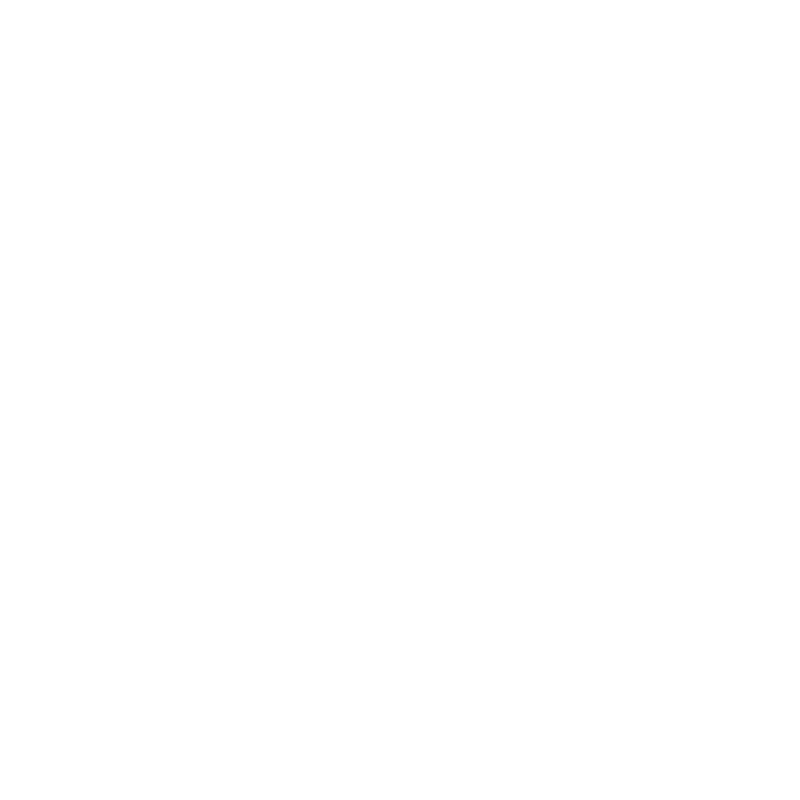
FMF胎児クリニック東京ベイ幕張では、入職者それぞれに合わせた学びや研修、サポート体制を通じて個人のスキルを高められる仕組みを整えています。
胎児医療や遺伝カウンセリング、超音波検査の高度な技術、英語力など、多岐にわたる学習機会が、質の高い医療に直結すると考えています。
患者さんが「困らずに済む」状態を実現し、医療従事者自身も達成感ややりがいを得ながら実績を積み重ねることで、スキルアップしていける好循環が生まれています。


ここでは、FMF胎児クリニック東京ベイ幕張の動画をご紹介します。患者さん目線で胎児医療を知るきっかけとして、ご覧ください。
胎児医療の従事者には、外国人患者の診療や国際学会の参加など、医療英会話のスキルを磨ける機会が豊富にあります。さらに英語でのカンファレンスや症例検討を通じて、グローバルに活躍できる力も身につけられます。
胎児医療の現場では、英語力を活かせる場面が日常的にあります。看護師をはじめとする医療スタッフは、外国人患者の対応に加えて、海外の医療者との情報交換やカンファレンスなど、英語を用いる環境に触れる機会があり、問診や検査のサポートなど、日々の業務を通じて語学力と専門知識の両面を高めていくことができます。
胎児医療では外国人患者の診療機会が多く、そこではわかりやすい説明と文化的な配慮が求められます。通訳を介さずに直接コミュニケーションを取るケースもあるため、医療英会話のスキルは非常に重要です。英語対応の経験を積むことで、外国人患者との信頼関係を築きやすくなり、より質の高い医療を提供できるようになります。
胎児医療は、医師、看護師、超音波検査士、遺伝カウンセラー、臨床検査技師が緊密に連携するチーム医療によって成り立っています。各職種が専門性を発揮することで、精度の高い診断と妊婦さんに寄り添ったケアが実現します。
胎児ドックとは、お腹の赤ちゃんの健康状態を詳細に評価するスクリーニング検査を指します。FMF(The Fetal Medicine Foundation)認定ライセンスを取得した医療者が胎児ドックを実施することで、適切なクオリティを担保することが可能になります。超音波検査の精度を向上させるためには、このような専門資格の取得や継続的なトレーニングが重要な要素となります。
妊婦さんやご家族に対して、赤ちゃんの染色体異常や遺伝子異常の可能性に関する情報を正確に伝え、意思決定をサポートするのが遺伝カウンセリングです。それは単なる情報提供ではなく、心理的なケアや価値観の尊重も求められます。カウンセラーは専門知識と高いコミュニケーション力を備え、医療チームの一員として妊婦さんを支援します。
臨床検査技師は、血液検査や遺伝子検査を担当してデータをそろえるのが役割であり、検査技師の分析データは診断に向けた重要な判断材料となります。胎児医療では精密なデータ分析力と高度な知識とスキルが求められます。臨床検査技師もまた、妊婦さんを支えるチーム医療に欠かせない存在として活躍しています。
妊娠初期・中期・後期で胎児超音波検査の目的は異なります。超音波検査士は目的を理解した上で、高精度な計測技術と画像解析能力が求められます。NT測定等のFMF認定資格の取得により、自身の技術向上とともに、標準化された胎児スクリーニングに携われるようになります。
胎児医療における看護師の役割は、診察の補助にとどまりません。妊婦さんやご家族への心理的な配慮をはじめ、検査前後のフォローや多職種との連携調整など業務は多岐にわたります。検査への不安を和らげ、安心して臨める環境を整える存在として、妊婦さんと医療チームをつなぐ橋渡しの役割を担っています。